2 第4次食育推進基本計画の構成と概要
第4次基本計画は、令和3(2021)年度からおおむね5年間を対象とする計画として作成されました。
第4次基本計画では、国民の健康や食を取り巻く環境の変化、社会のデジタル化など、食育をめぐる状況を踏まえ、<1>生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進、<2>持続可能な食を支える食育の推進、<3>「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進の3点を重点事項として掲げました。また、第4次基本計画では、その内容を、「はじめに」、「食育の推進に関する施策についての基本的な方針」、「食育の推進の目標に関する事項」、「食育の総合的な促進に関する事項」、「食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項」の構成の中で具体的に説明しています。
【はじめに】
「はじめに」では、食をめぐる現状について基本的な認識を示しています。
平成17(2005)年に「食育基本法」が制定され、国は15年にわたり多様な関係者とともに食育を推進してきたことに触れました。そして、高齢化が進行する中で、健康寿命の延伸や生活習慣病の予防が引き続き国民的課題であり、栄養バランスに配慮した食生活の重要性は増している一方で、食に関する国民の価値観や暮らしの在り方も多様化し、健全な食生活を実践することが困難な場面も増えてきていることや、地域の伝統的な食文化が失われていくことへの危惧を示しています。また、食の供給面では、農林漁業者や農山漁村人口の高齢化・減少が進む中、食料自給率が低下している一方、食品ロスが発生しているということや、異常気象に伴う自然災害の頻発等、地球規模の気候変動の影響が顕在化しており、食の在り方を考える上で環境問題を避けることはできなくなっていることにも触れています。
加えて、国際的な観点として、平成27(2015)年9月の国連サミットで採択された「SDGs(*1)(持続可能な開発目標)」にも、栄養改善や教育、持続可能な生産消費形態の確保などの食育に関係の深い目標があり、食育の推進は、SDGsの達成に寄与するものであるとしています。
さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は、人々の生命や生活のみならず、行動・意識・価値観にまで波及し、「新たな日常」の中でも、食育が多くの国民による主体的な運動となるためには、社会のデジタル化の進展も踏まえ、デジタルツールやインターネットも積極的に活用していくことが必要という、新たな認識を示しています。
こうした情勢を踏まえ、令和3(2021)年度からおおむね5年間を対象とする第4次基本計画を作成、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとしています。
*1 Sustainable Development Goalsの略。平成28(2016)年から令和12(2030)年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っている。
【食育の推進に関する施策についての基本的な方針】
食育の推進に関する施策についての基本的な方針として、国民の健康や食を取り巻く環境の変化、社会のデジタル化など、食育をめぐる状況を踏まえ、今回新たに設けられた3つの重点事項と、7つの基本的な取組方針を掲げています。
重点事項は、以下の3つです。
重点事項(1)生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進
国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むためには、妊産婦や、乳幼児から高齢者に至るまで、多様な暮らしに対応し、家庭、学校・保育所等、地域の各段階において、切れ目なく生涯を通じた心身の健康を支える食育を推進することが重要です。
このため、「人生100年時代」に向けて、生活習慣病の予防や健康寿命の延伸を実現し、全ての国民が健全で充実した食生活を実現することを目指し、家庭、学校・保育所、職場、地域等の各場面において、地域や関係団体の連携・協働を図りつつ生涯を通じた食育を推進します。
加えて、健康や食に関して無関心な層も含め、デジタルツールや行動経済学に基づく手法の1つであるナッジ(そっと後押しする:人々がより良い選択を自発的に取れるように手助けする手法)を活用する等、自然に健康になれる食環境づくりを推進します。
重点事項(2)持続可能な食を支える食育の推進
国民が健全な食生活を送るためには、その基盤として持続可能な環境が不可欠であり、食育関係者を含む国民が一体となって、食を支える環境の持続に資する食育を推進します。
(食と環境との調和:環境の環(わ))
国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っていることを認識し、食料の生産から消費等に至る食の循環が環境に与える影響に配慮する必要があります。また、食品ロスの削減に取り組むことにより、食べ物を大切にするという考え方の普及や環境への負荷低減を含む各種効果が期待されます。
このため、生物多様性の保全に効果の高い食料の生産方法や資源管理等に関して、国民の理解と関心の増進のための普及啓発、持続可能な食料システム(フードシステム)につながるエシカル消費(*2)の推進等、環境と調和のとれた食料生産とその消費に配慮した食育を推進します。
*2 人や社会、環境に配慮した消費行動
(農林水産業や農山漁村を支える多様な主体とのつながりの深化:人の輪(わ))
食料の生産から消費等に至るまでの食の循環は、多くの人々の様々な活動に支えられており、そのことへの感謝の念や理解を深めることが大切です。
このため、農林漁業体験の推進、生産者等や消費者との交流促進、地産地消の推進等、食の循環を担う多様な主体のつながりを広げ深める食育を推進します。
(日本の伝統的な和食文化の保護・継承:和食文化の和(わ))
日本の伝統的な和食文化の保護・継承は、国民の食生活の文化的な豊かさを支える上で重要であるとともに、地域活性化等に寄与し、持続可能な食に貢献することが期待されます。また、和食は栄養バランスに優れ、長寿国である日本の食事は世界的に注目されています。
このため、食育活動を通じて、郷土料理、伝統料理、食事の作法等、伝統的な地域の多様な和食文化を次世代へ継承するための食育を推進します。
これらの持続可能な食に必要な、環境の環(わ)、人の輪(わ)、和食文化の和(わ)の3つの「わ」を支える食育を推進します。
重点事項(3)「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進
上記(1)及び(2)に示した重点事項に横断的に取り組むため、「新しい生活様式」に対応し、「新たな日常」においても食育を着実に実施するとともに、より多くの国民による主体的な運動となるよう、ICT等デジタル技術を有効活用して効果的な情報発信を行うなど、新しい広がりを創出するデジタル化に対応した食育を推進します。また、「新たな日常」は、食生活を見直す機会にもなることから、栄養バランス、食文化、食品ロス等、食に関する意識を高めることにつながるよう食育を推進します。
基本的な取組方針
基本的な取組方針については、「国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成」、「食に関する感謝の念と理解」、「食育推進運動の展開」、「子供の食育における保護者、教育関係者等の役割」、「食に関する体験活動と食育推進活動の実践」、「我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献」、「食品の安全性の確保等における食育の役割」の7つの点からまとめています。
【食育の推進の目標に関する事項】
目標については、国民運動として食育を推進するにふさわしい定量的な目標を掲げました(図表1-3-2)。特に第4次基本計画においては、SDGsの考え方を踏まえた食育の推進や重点事項に対応した食育の推進の観点から、新たに7つの目標値を設定するなどの見直しを行い、その結果、24の定量的な目標値を定めています。具体的には、重点事項(1)生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進として、栄養バランスに配慮した食生活の実践を促すため、健康寿命の延伸を目指す「健康日本21(第二次)」の趣旨を踏まえ、「<11>1日当たりの食塩摂取量の平均値」、「<12>1日当たりの野菜摂取量の平均値」、「<13>1日当たりの果物摂取量100g未満の者の割合」を目標値として新たに設定しました。また、重点事項(2)持続可能な食を支える食育の推進として、我が国の食の持続可能性を高めるため、農林水産業や農山漁村を理解し主体的に支え合う行動を促すべく「<18>産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民の割合」を、環境への負荷を減らすために環境に配慮した購買行動を促すべく「<19>環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民の割合」を、食文化を着実に次世代へ継承していくために様々な場面で食べることを促すべく「<22>郷土料理や伝統料理を月1回以上食べている国民の割合」を目標値として新たに設定しました。
このほか、子供たちに対する地域の自然、文化、産業や食に関する理解を深める指導を充実させるため「<6>栄養教諭による地場産物に係る食に関する指導の平均取組回数」を新設しました。また、学校給食における地場産物等を使用する割合については、生産者や学校給食関係者の努力を適切に反映するとともに、地域への貢献等の観点から、その割合を食材数ベースから金額ベースに見直し、現状値から維持・向上した都道府県の割合を目標とすることとしました。
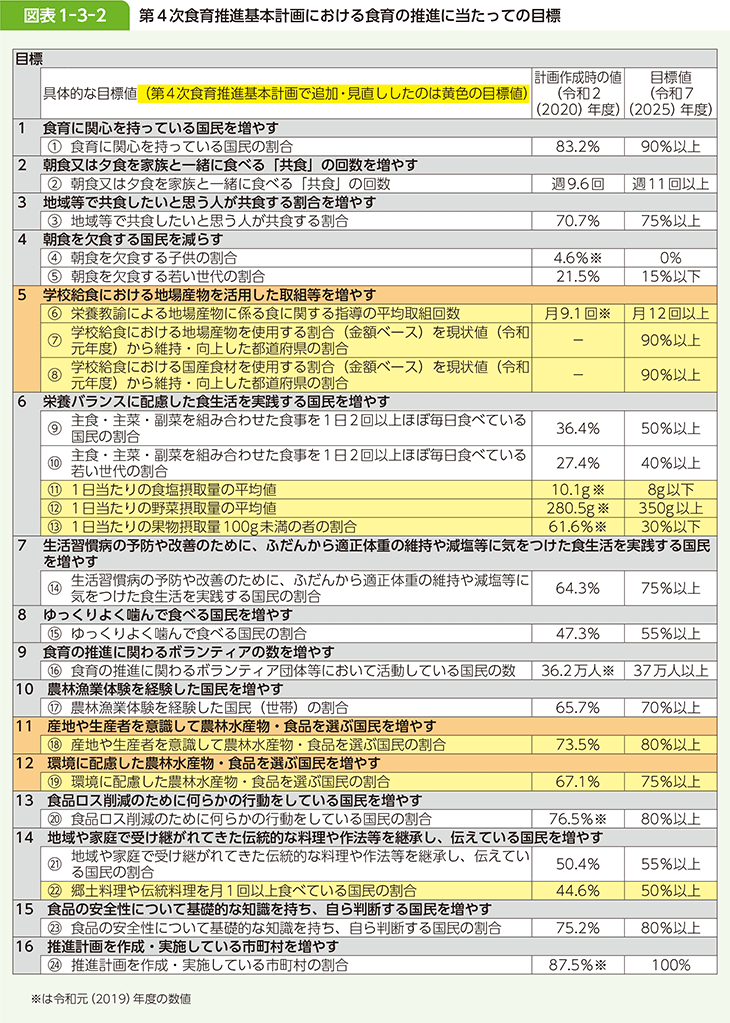
【食育の総合的な促進に関する事項】
食育の総合的な促進については、7項目にわたる国の取り組むべき基本施策を取りまとめ、地方公共団体等もその推進に努めることとされています。
(1)家庭における食育の推進
家庭において、基本的な生活習慣づくりへの意識を高め、生涯にわたって切れ目なく、心身の健康の増進と豊かな人間性を育む基盤づくりを行うことができるよう、(i)子供の基本的な生活習慣の形成、(ii)望ましい食習慣や知識の習得、(iii)妊産婦や乳幼児に対する食育の推進、(iv)子供・若者の育成支援における共食等の食育推進、(v)在宅時間を活用した食育の推進、の各施策に取り組むこととしています。
(2)学校、保育所等における食育の推進
学校、保育所等は、子供への食育を進めていく場として大きな役割を担うため、栄養教諭・管理栄養士等を中核として、保護者や地域の多様な関係者との連携・協働の下で、体系的・継続的に食育を推進するよう、(i)食に関する指導の充実、(ii)学校給食の充実、(iii)食育を通じた健康状態の改善等の推進、(iv)就学前の子供に対する食育の推進、の各施策に取り組むこととしています。
(3)地域における食育の推進
生涯にわたる心身の健康を確保するため、家庭、学校・保育所、生産者、企業等と連携・協働し、地域における食育を推進するため、(i)「食育ガイド」等の活用促進、(ii)健康寿命の延伸につながる食育の推進、(iii)歯科保健活動における食育推進、(iv)栄養バランスに優れた日本型食生活の実践の推進、(v)貧困等の状況にある子供に対する食育の推進、(vi)若い世代に関わる食育の推進、(vii)高齢者に関わる食育の推進、(viii)食品関連事業者等による食育の推進、(ix)専門的知識を有する人材の養成・活用、(x)職場における従業員等の健康に配慮した食育の推進、(xi)地域における共食の推進、(xii)災害時に備えた食育の推進、の各施策に取り組むこととしています。
(4)食育推進運動の展開
食育に係る関係者や食育に新たな広がりをもたらす多方面の分野の関係者が主体的かつ多様に連携・協働して地域レベルや国レベルのネットワークを築き、明るく楽しく多様な食育推進運動を国民的な広がりを持つ運動として全国的に展開していくため、(i)食育に関する国民の理解の増進、(ii)ボランティア活動等民間の取組への支援、表彰等、(iii)食育推進運動の展開における連携・協働体制の確立、(iv)食育月間及び食育の日の取組の充実、(v)食育推進運動に資する情報の提供、(vi)全国食育推進ネットワークの活用、(vii)「新たな日常」やデジタル化に対応する食育の推進、の各施策に取り組むこととしています。
(5)生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等
食を生み出す場としての農林漁業に関する理解を深めるとともに、農林水産業・食品産業の活動が自然資本や環境に立脚していることから、その持続可能性を高めるよう、環境と調和のとれた食料生産とその消費にも配慮した食育を推進するため、(i)農林漁業者等による食育の推進、(ii)子供を中心とした農林漁業体験活動の促進と消費者への情報提供、(iii)都市と農山漁村の共生・対流の促進、(iv)農山漁村の維持・活性化、(v)地産地消の推進、(vi)環境と調和のとれた持続可能な食料生産とその消費にも配慮した食育の推進、(vii)食品ロス削減に向けた国民運動の展開、(viii)バイオマス利用と食品リサイクルの推進、の各施策に取り組むこととしています。
(6)食文化の継承のための活動への支援等
我が国の伝統的な食文化を次世代に継承していくためには、地域の多様な食文化を支える多様な関係者による活動の充実が必要です。また、和食文化の保護・継承は持続可能な食の実現に貢献することが期待されます。このため、(i)地域の多様な食文化の継承につながる食育の推進、(ii)ボランティア活動等における取組、(iii)学校給食等での郷土料理等の積極的な導入や行事の活用、(iv)専門調理師等の活用における取組、の各施策に取り組むこととしています。
(7)食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進
国民の食に関する知識と食を選択する力の習得や、健全な食生活の実践に資するよう、食に関する国内外の幅広く正しい情報提供等を行うため、(i)生涯を通じた国民の取組の提示、(ii)基礎的な調査・研究等の実施及び情報の提供、(iii)リスクコミュニケーションの充実、(iv)食品の安全性や栄養等に関する情報提供、(v)食品表示の理解促進、(vi)地方公共団体等における取組の推進、(vii)食育や日本食・食文化の海外展開と海外調査の推進、(viii)国際的な情報交換等、の各施策に取り組むこととしています。
【食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項】
上記に加えて、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項として、<1>多様な関係者の連携・協働の強化、<2>地方公共団体による推進計画に基づく施策の促進とフォローアップ、<3>積極的な情報提供と国民の意見等の把握、<4>推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用、<5>基本計画の見直しの5項目が定められています。
コラム:持続可能な食を支える環境の整備に向けた取組
我が国の近年の食料・農林水産業を取り巻く状況は、生産者の減少・高齢化などの生産基盤の脆弱化や、地域コミュニティの衰退が進み、また、地球温暖化に伴う農産物の品質低下や大規模災害の激甚化が顕在化していることに加えて、新型コロナを契機としたサプライチェーンの混乱等、大変厳しいものとなっています。地球環境問題の面からも、食料・農林水産業が利活用してきた土地や水、生物資源などのいわゆる「自然資本」の持続性にも大きな危機が迫っています。こうした中、様々な産業で、SDGsや環境への対応が重視されるようになり、今後、我が国の食料・農林水産業においても的確に対応していく必要があります。EU(欧州連合)が令和2(2020)年5月に「ファームtoフォーク戦略」として化学農薬・肥料の削減目標を打ち出すなど、国際社会は既に動き始めています。また、国際的な議論の中で、我が国としてもアジアモンスーン地域の立場から、新しい食料システムを提案していく必要があることから、農林水産業や地域の将来も見据えた持続可能な食料システムの構築が急務となっています。
このため、農林水産省では、令和2(2020)年10月から、我が国の食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるための「みどりの食料システム戦略」の検討を開始し、令和3(2021)年3月に中間取りまとめを決定しました。本戦略においては、革新的な技術・生産体系を順次開発し、社会実装することにより、令和32(2050)年までに目指す姿として、農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現、化学農薬の使用量をリスク換算で50%低減、化学肥料の使用量を30%低減、耕地面積における有機農業の取組面積の割合を25%(100万ha)に拡大、等の目標を掲げています。さらに、令和12(2030)年までに食品製造業の労働生産性を最低3割向上、食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現を目指すこととしています。
これらの実現のため、(1)資材・エネルギー調達における脱輸入・脱炭素化・環境負荷軽減の推進、(2)イノベーション等による持続的生産体制の構築、(3)ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立、(4)環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進等について、それぞれ今後の具体的な取組を示しています。
食育に関する取組としては、特に(4)環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進について、「栄養バランスに優れた日本型食生活の総合的推進」の中で、栄養バランスに優れた日本型食生活に関する食育、地産地消の推進や持続可能な地場産物や国産有機農産物等を学校給食に導入する取組の推進等を実施するとしています。
こうした動きを踏まえ、第4次基本計画では、「取り組むべき施策」として「環境と調和のとれた持続可能な食料生産とその消費にも配慮した食育の推進」を掲げており、有機農業を始めとした持続可能な農業生産や持続可能な水産資源管理等、生物多様性と自然の物質循環を健全に維持し、自然資本を管理し、又は増大させる取組に関して、国民の理解と関心の増進のため普及啓発を行うとしています。例えば学校給食での有機食品の利用などの有機農業を地域で支える取組事例の共有や消費者を含む関係者への周知が行われるよう、有機農業を生かして地域振興につなげている地方公共団体の相互の交流や連携を促すネットワーク構築を推進します。
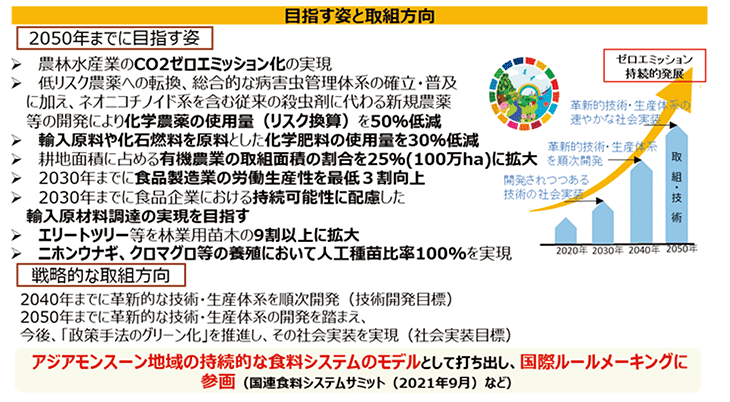
みどりの食料システム戦略 中間取りまとめ(概要)抜粋
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125
FAX番号:03-6744-1974




